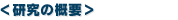

 |
| 皮質骨リモデリングin
vivo実験モデルの基礎的検討 |
|
 |

1.緒言
骨組織の力学的リモデリングは典型的な生体組織の機能的適応の例として広く知られているが、力学的負荷とそれによる骨リモデリング作用の定量的関係を明らかにするような十分な精度を持つ生体力学的実験結果がない。
そこで本研究では、構造要素として重要な役割を果たしている皮質骨のリモデリングを定量的に評価するin
vivo実験モデルの開発を目指す。そのためにまず、負荷履歴が明らかな新生骨組織を生体内で誘導できるような実験システムの開発を行った。具体的には、フレーム型デバイスを開発し、ラット脛骨に埋入してフレーム内に新生骨を生成する実験を試みた。さらに、整形外科で臨床に広く用いられている骨延長術を応用した新生骨誘導実験を行った。
2.実験装置及び手順
骨組織は、組織の発生または新生の過程において、形成作用(モデリング)と力学環境の変化に対する再構築作用(リモデリング)の影響を同時に受けている。よって骨リモデリングの評価のためには、対象となる試料の負荷履歴をも考慮する必要があると考えられる。しかし、生体内の骨組織を用いてリモデリング実験を行う場合、試料の初期状態は全て異なっており、またそれらを規定することも困難である。
そこで本研究では生体内に新生骨組織を誘導し、その形成過程で作用する負荷を制御することで負荷履歴の明らかな骨組織を作る手法を検討した。

2.1フレーム型デバイスによる実験モデル
まず、基礎実験として実験領域を規定するための以下の3種類のフレームを骨に埋入し、フレーム内に骨組織を誘導する実験を行った。
(1) 15×2×0.5 mmのプレート2枚を骨幹軸に対して平行に埋入
(2) 2×2×0.5 mmのプレート2枚を骨幹軸に対して平行に埋入
(3) 12×3×2 mmのブロックに10×2 mmの開口部のある口型フレームを埋入
実験モデル(1)、(2)により、オステオンの配向性の骨誘導への影響を調査できると考えた。
また実験モデル(3)では、誘導領域を周囲の骨組織から隔離した状態での骨誘導の可能性を調査できると考えた。また骨組織の本来の再生能を知るため、(4)
骨欠損のみ作製した実験も行った。

実験手順を以下に示す。
実験動物にはラット(Std:Wister/ST)を用いた。麻酔下で右脛骨にフレームを埋植した。実験モデル(1)では2枚のプレートの間隔を約1mmとした。また、実験モデル(2)では、2枚のプレートの間隔を約10
mm、欠損の幅を約1 mmとした。実験モデル(4)では欠損部の幅を1mmとした。実験モデル(3)の埋植手術時の様子を図1に示す。
各モデル、それぞれ3体のラットで実験を行った。手術後、ケージ内で特に運動の制限を与えずに飼育した。
|
|

2.2創外固定型デバイス
整形外科では骨折整復のための創外固定器を利用した骨延長術により、腫瘍摘出により失われた骨組織の修復や骨格の不釣り合いの改善が行われている[1]。そこで本実験ではRichardsらの実験[2]を参考に、ラット用創外固定器を開発し、それを用いた骨延長術を試みた(実験モデル(5))。
試作した創外固定器は2つのブロックを2本のガイドと1本のネジで連結したもので、ネジを回転させることによりプロック間距離が調節可能である。ブロックはピン(φ1
mmのキルシュナー鋼線)により骨と結合する。

|
|
実験手順を以下に示す。
まず、麻酔下でラット(Std:Wister/ST)右大腿骨に経皮的にピンを刺入し、創外固定器を装着した。次にピン刺入位置から約5mm背側の皮膚を大腿骨と平行にメスで切開し、大腿骨を露出させた。マイクロサージカルソーにより、大腿骨を2つに切断した。二分された大腿骨は切断面が互いに接触するよう固定器のブロック間隔をネジにより調整した後、切開部を縫合した(図2)。術後、ラットはケージ内で抗生物質を適宜投与しながら飼育した。ケージ内での運動、食事に特に制限を与えず6日間経過した後、1日2回、1回につき0.25mm、すなわち1日あたり0.5
mmずつの骨延長を4日間施した。さらに延長をせずに4日間飼育したのちに屠殺し、マイクロX線CTにより骨内部構造を観察した。
|

3.実験結果

 実験モデル(1)〜(3)によるフレーム埋殖実験では、フレームの脱落や欠損部周辺での骨折のため、どのモデルによっても新生骨誘導ができなかった。フレームを埋植しなかった実験モデル(4)では、4週間後には外観上、欠損が塞がった。 実験モデル(1)〜(3)によるフレーム埋殖実験では、フレームの脱落や欠損部周辺での骨折のため、どのモデルによっても新生骨誘導ができなかった。フレームを埋植しなかった実験モデル(4)では、4週間後には外観上、欠損が塞がった。
欠損作成後4週及び8週経過後に屠殺し、マイクロCTにより内部構造の観察を行った結果を示す。図3は4週経過後の、図4は8週経過後の観察結果を示す。
4週経過時で脛骨表面は塞がっていたが、内部には空孔や海綿骨様の組織が見られた。実験領域は脛骨骨幹中央なので、本来、海綿骨組織はない。したがって、この海綿骨様の構造は再生過程で形成されたwoven
boneの名残りと考えられ、完全な皮質骨組織としては再生していないといえる。
4週経過時では欠損部に再生した皮質骨が確認できるが、その厚さは欠損部以外の領域や、未処置の左脛骨の対応する部位との比較においても薄かった。また内部の海綿骨様の空孔構造も残存したままであった。 |

創外固定器による骨延長実験では、摘出した大腿骨のうち、実験期間中に固定器の脱落、感染症による患部のひどい化膿、体調不良による衰弱などの明らかな問題が発生しなかったもの4体について、マイクロX線CTによる内部構造観察を行った。
その結果の例の側面像を図5に、断面像を図6に示す。
側面像に見られるとおり、切断面が平行を保った状態で骨延長されており、固定器の装着と延長作業が良好に実施されたことがわかる。また断面像には骨折治癒過程初期に形成されるwoven
boneに特徴的な編目構造が観察できたことから、新生骨組織形成が順調であると考えられる。
|
4.考察
実験モデル(1)〜(3)におけるフレームの脱落は、骨に対する固定性の悪さに起因すると考えられる。本実験では負荷履歴の明らかな新生骨組織を形成することを目的としたため、骨セメント等を用いず、はめ合わせによる固定を行ったが、生体内に精度の良い手加工を施さなくてはならず、手技の難度が非常に高かった。また、実験領域を広くとるためにフレームをある程度大きくせざるを得なかったため、フレーム埋入のための孔が大きくなり過ぎた。実験モデル(4)では皮質骨の完全な回復が得られなかった。これは、通常の体重支持機能が欠損部以外の骨組織により十分に果たされたため、新生組織へ作用する負荷が小さく、組織の成長速度が緩やかになったためと考えられる。したがって、新生組織に十分な負荷を作用することができれば、より速やかな組織形成が可能であると期待できる。
実験モデル(5)では、新生骨組織の前駆組織であるwoven boneが観察できた。よって、十分な実験期間をとることで新生皮質骨組織が得られることが期待できる。
5.結言
本研究では力学的骨リモデリングの定量的評価を行うために不可欠な、負荷履歴が明らかな骨組織の形成を行うための基礎実験を行った。その結果、創外固定法を用いた骨延長術を応用することにより新生骨誘導が可能であることが示された。今後は手術成功率高上のための実験器具と手術手順の改良、新生組織に力学負荷を作用させる機構開発が必要である。



| [1]
|
井上四郎他, 創外固定法テクニックマニュアル, 1993, 南江堂 |
| [2]
|
Richards, M, Huibregtse, BA, Caplan,
AI, Goulet, JA, Goldstein, SA, Marrow-derived
Progenitor Cell Injections Enhance New
Bone Formation during Distraction, J.
Orthopaedic Research , Vol. 17, 1999,
pp. 900-908. |
|
|
|


